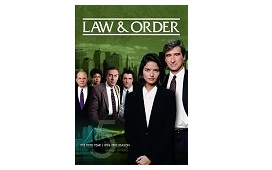通算107話「殺人ヘルメット」
留置場に入れられた少年が、突然壁に自分で頭を打ちつけ始め、死亡する。被害者は自閉症児で施設に入れられており、そこでは治療として虐待まがいの施術が日常的に行われていた。
Law & Order: the Fifth Year DVD (米国版 リージョン1)
- 脚本:René Balcer, Michael S. Chernuchin
- 監督:Matthew Penn
- 初回放映:1995-04-19
People v. Alan Colter (判事:Joseph Rivera)
街で通行人に絡み、留置場に入れられた少年が死亡する。突然何かを叫んで壁に頭を打ち付け始めたため、ローガンが取り押さえようとしたが、間に合わなかったのだ。留置場での死亡ということで、ローガンは内部調査を受けるが、すぐに疑いは晴れる。被害者には長期間にわたって拘束されて虐待された形跡があった。ただし性的な外傷はない。
服装からホームレスでないことがわかり、失踪人を調べた結果、被害者はケヴィン・ジェフリーズと判明。自閉症で行動管理クリニックという施設に入れられていたが、そこから逃げ出していた。拘束の跡は、自傷行動を抑えるための処置だったとわかる。
ケヴィンの死因は首にあった血の塊が破裂したことで、外傷の多くは自傷によるものとわかるが、それ以外に感電による火傷の跡がいくつも発見される。クリニックを経営するコルター医師によると、それは自傷に対する「懲罰」であり、州による認可を受けた方法で保護者の同意を得た場合にのみ限られた部位に行われている治療であるという。だが、ケヴィンの身体に残る傷は表向きの説明を大きく超えている。
ローガンとブリスコーは、以前にコルター医師を訴えたデイヴィッドソン夫人の存在を突き止め、クリニックで行われていた虐待まがいの「治療」の実態について話を聞く。コルターは、外の音を遮断して雑音を聞かせる「バズ・ボックス」という赤いヘルメットを使っていたが、そのヘルメットにより首にケヴィンと同じような血の塊が形成されることがわかる。訴訟の後、そのヘルメットは使用を禁じられているはずだった。
刑事たちはクリニックを捜索し、州のガイドラインを超える感電治療を行っている現場を発見して職員を逮捕するが、赤いヘルメットは発見できなかった。
コルター医師が行っていた施術が虐待であるか医療行為であるかをめぐり、判事は患者の保護者たちから話を聞く。保護者たちはいずれも、施術が州のガイドラインを超えていることを知りつつ「効果があればそれでも良い」と同意していた。判事はその意見を聞いてコルター側の言い分を認める。
患者たちへの傷害罪が立件できない以上、赤いヘルメットを探し出してケヴィンの死と結び付けるより方法はないが、ヘルメットは見つからない。すでに廃棄されたものと思われた。
その後、クリニックを解雇された元職員から「赤いヘルメットはデイヴィッドソン事件以降も、使用回数が減っただけで使用は続けられていた」という情報が提供される。それに対抗してコルター側は、ケヴィンと同室だったデイヴィッド・ヴィラーディを目撃証人とし、ヘルメットが使われていなかったことを証言させようとする。デイヴィッドは自閉症で言葉を話せないが、母親の補助でキーボードを使ってコミュニケーションができるという。
デイヴィッドはマッコイの前で「ケヴィンが赤いヘルメットを被っている所は見たことがない」とキーボードで打ってみせるが、その手は母親にしっかりと捕まれており、母親が誘導しているように見える。マッコイによる実験で、デイヴィッドの回答はやはり母親が誘導したものとわかる。とは言え検察側の証人も、クリニックを解雇された(恨みを持つ)元職員1人だけで材料が足りない。
そこでマッコイはデイヴィッドの(実際は母親の)最初の供述に注目する。デイヴィッドが入所したのは、赤いヘルメットの使用が禁止された後であり、かつ検察の方からヘルメットが何色かは一言も説明していなかったのに、ヴィラーディ夫人は「赤いヘルメットは見たことがない」と述べていたのだ。
マッコイの追及に対し、ヴィラーディ夫人はようやく赤いヘルメットを見たことを認めるが、それはケヴィンではなく自分の息子に使用されたのだ。だがそれでも「ヘルメットよりデイヴィッドの自傷行為の方がもっと酷かった」と言う。
コルター側は取引に応じ、2年以上6年以下の収監刑を言い渡される。ヴィラーディ夫人は「クリニックが閉鎖されたので息子は居場所がなくなってしまった、貴方が代わりに面倒を見てくれるとでもいうのか」とマッコイを非難する。
虐待まがいの「治療」行為をめぐる事件。劇中ではオリヴェット医師が登場し、このクリニックで行われている嫌悪療法 (aversion therapy) は時代遅れだと批判する。自傷行為を行った時にビリッと感電させるので、一時的には良くなったように見えるが、患者が痛みに慣れるとまた元に戻ってしまうので、より強い痛みを与えざるを得なくなる。実際にコルター医師は感電治療の電圧を上げていたわけで、「それは要するに効いてないってことなんじゃ……」という疑問もわいてこようというもの。
患者の母親はそれでも自傷行為よりマシだと言うが、このまま嫌悪療法をただエスカレートさせるだけなら、遅かれ早かれケヴィンと同じ運命をたどる羽目になったのではないだろうか。
ヴィラーディ母子が行っていた「ファシリテイテッド・コミュニケーション (FC)」については、日本でも「奇跡の詩人」という番組をめぐって話題になったことがあった。下記の本の他にも、「奇跡の詩人」で検索してみるといろいろ情報が出てくる。
- 『異議あり!奇跡の詩人』滝本太郎、石井 謙一郎
本当の意味でのFCって現実に可能なのだろうか。可能だとしても、介助する側とされる側の距離が容易に近づきすぎてしまい、結局は誘導してしまう(それも、介助者の側に誘導しているという意識がないままに)ことになるような危うさを感じた。
このエピソードに出てくるケースはどう見てもインチキだが、介助者にその意識はあったのかな。審問でマッコイが行った実験は、母親が後を向いている間に息子に鳥の絵を見せ、「何の絵だったか?」と聞くというものだったが、結果は2回やって2回とも間違いだった。母親は「これは不当だ」と怒り出すが、コルター医師にもそれは説明できないのだからしょうがない。彼女は自分がタイプしている自覚があったのだろうか。それともコックリさん状態で息子がしゃべっていると信じていた?(でもよく注意していたら、判事とマッコイが紙をやり取りする時に、裏から透けて見えそうな気もしたけど……)
そうして嘘が暴かれた後でも、ヴィラーディさんの怒りの対象は、自分をだましてきたコルターではなく、その嘘を暴いたマッコイなんだよね。デイヴィッドソンさんのように、もっと良い施設を見つけられれば良いのだが。
2010-06-29